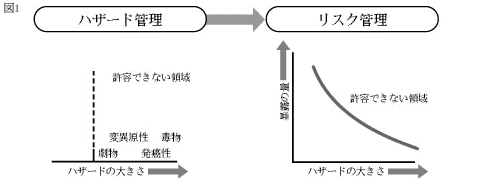ハザード管理からリスク管理へ
1970年代には発がん物質を中心に、「有害な化学物質 はゼロであるべきである」というゼロ志向の考えが 支持され、極めて過剰な安全性が求められていました。すなわち、発 がん性など重篤度の高いと思われるハザード項目について 該当する化学物質を指定し、その量に関係なく、その物質の存 在自体を強力な管理下で規制しようとするものであり、一度何らかの有害物質に指定されると、場合によっては、その化学物質はこの世の中から抹殺されるほどでした。 この「ハザード管理」の考え方は、ダイオキシンや環境ホルモンなど、「疑わしきは使わない」という所謂「ゼロリスク」の考え方として現在でも受け継がれています。
しかしながら、この様な考え方では、影響の量依存性に関する情報がなくても、完全に密封された状態に封じ込まれたものについては問題ありませんが、例えばPCBのように、土壌中や食物の中に現にある量が存在する場合には、どの程度の量であればどの様な危害が起こるか、どの程度の量までなら許容できるかなどの判断ができず、対処の目標も方策も定まりません。
これに対し、1980年代に入って「全ての化学物質は何らかの有害性を有しており、有害になるか否かはその量に依存する」という、「影響の量依存性」の考え方が盛んに議論され始めました。
この考え方では、化学物質を単にハザードの大きさで評価するのではなく、その化学物質が影響を受ける対象(ヒト、生態系、設備など)とどの様な状況で接触しているかという、 暴露の要素も加味して影響の大きさを評価し、ハザードの大きさと暴露量との積で表される領域のうち、許容できない領域に存在するものを、何らかの手段によって許容できるレベまで下げようという「リスク管理」の考え方です。つまり、ハザードの大きい物質でも、その物質の暴露量を下げれば安全は確保できるし、逆に、ハザードが小さくても、暴露量が大きい場合には対策を講じなければなりません。
この「リスク管理」は図1で示すように、「ハザード管理」に比べて選択の幅が広がり、種々の対策を講ずる余地が与えられます。さらに、ダイオキシンの様に使い道のない物質は別として、全ての化学物質は人間の生活に何らかの有益な役目を果たしており、それによって我々の豊かな生活が実現しています。この場合、一般的には、「有益な物は、ある程度のリスクは容認する」という感覚を持つことであり、この様な考え方で化学物質を管理することは馴染みが薄いけれども、今後ますます必要になると考えます。